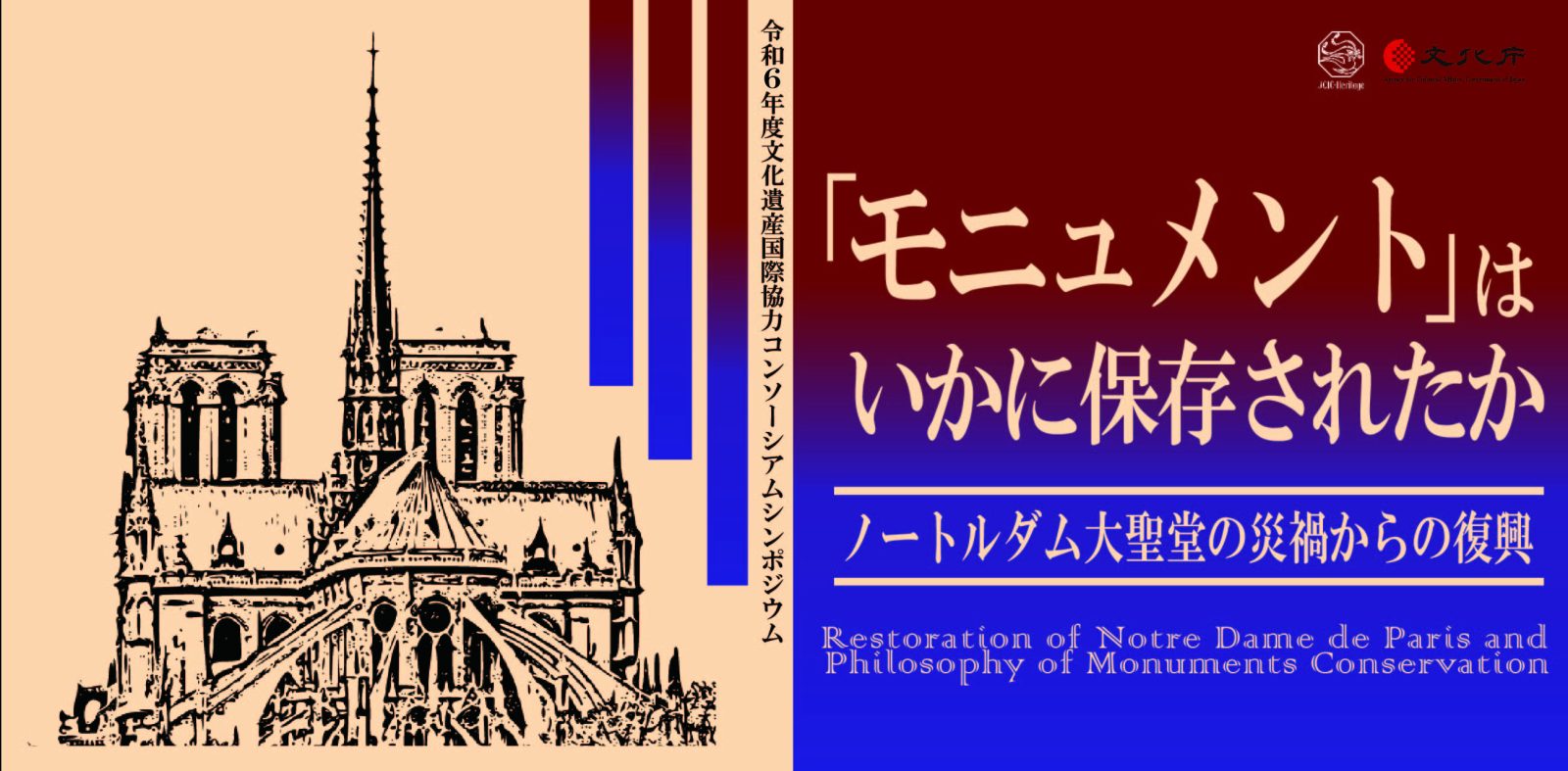文化遺産国際協力コンソーシアムは、2024(令和6)年11月30日(土)に文化庁との共催で令和6年度シンポジウム「〈モニュメント〉はいかに保存されたか:ノートルダム大聖堂の災禍からの復興」を東京富士大学二上講堂にて開催しました。
※シンポジウムの開催概要・プログラムについては、こちらをご覧ください。
本シンポジウムでは、2019年4月に発生した火災からの復興をとげたノートルダム大聖堂が2024年12月に一般公開される機会を捉え、「モニュメント」保存の長い歴史と伝統をもつフランスにおいて、焼失した木造部分の復旧を中心とした今回の修復工事で「オーセンティシティ」がどのように認識され、実際の修復方法にいかに適用されたかを振り返るとともに、奈良文書が提起した木造建築や修復技術の「オーセンティシティ」が今回の修復工事の考え方や修復方法にどのような影響を与えたかについて、日中仏の専門家による講演と議論を行う場としました。
シンポジウムは、青柳正規(文化遺産国際協力コンソーシアム会長)の開会挨拶で始まりました。まず奈良文書の意義は、西欧を中心にかたちづくられてきた「モニュメント」の概念を下地としたベニス憲章の考え方が更新できることを示し、その後の世界遺産を、ある意味で本当の「世界」の遺産におし広げたことにある、との認識が述べられました。そして、遺産の多様化とともに複雑さを増す「モニュメント」や「オーセンティシティ」といった考え方をいかに多くの人々が共有できる概念にしていけるかという難題を前に、ノートルダム大聖堂の木造部分の災害復旧という極めて具体的な例を通して議論を行うことで、いま一度遺産保護の原点にたち戻り、その本来の意味や目的を浮かびあがらせたい、という今回のシンポジウム企画の大きな背景が語られました。
続く、友田正彦(文化遺産国際協力コンソーシアム事務局長)による趣旨説明では、ノートルダム大聖堂の火災から復興までの大きな流れや、修復工事にいたる経緯が紹介されるとともに、その中で文化遺産としてのオーセンティシティがどのように意識され、実際の修復の仕事に適用されたかをこの機会に整理しておくことの重要性が強調されました。また、建築遺産の修復における復原や失われた建築の再建といった、それぞれ性格の異なる具体例を通して、ベニス憲章や奈良文書に対する理解やその受容のあり方を比較し、遺産保護の国際規範としての意義や影響を再考しようとする本シンポジウムの趣旨とあわせ、プログラムの概要が説明されました。
フィリップ・ヴィルヌーヴ氏(ノートルダム大聖堂修復事業技術者、歴史的記念物主任建築家)による基調講演1「ベニス憲章と奈良ドキュメントの観点から見たノートルダム大聖堂の再建と修復」(ビデオ出演)では、火災による深刻な被害状況の報告とともに、5年という限られた期間の中でどのような注意を払いながら今回の復旧と再建に取り組んだのかが報告されました。大聖堂を被災前の状態、すなわち19世紀にヴィオレ・ル・デュクによって大々的に修復された姿そのままに復するという大方針のもと、修復プロセスの各段階で「オーセンティシティ」の判断を行いながら、再建部分の外見を自然に調和させながら、その下にある既存の部材や被災した部材の保存にも注力したことが述べられました。特に、今回ほぼ全てを新材で再建することになった、中世以来の状態を留めていた小屋組については、奈良文書で示された「オーセンティシティ」の考え方を意識し、大聖堂の存続を支えてきた聖職者や信徒、職人の精神性に依拠し、樹木の選定や伐採に関わる儀式、伝統的な技法による加工や接合、組立などを重視したことが説明されました。最後に、大聖堂が今日まで存在し続けてきた裏には、ヴィオレ・ル・デュクほかの修復家のみならず様々な人々の思いや仕事の積み重ねがあることが述べられ、今回の修復工事を通じてヴィルヌーヴ氏もその一員に加わったことへの感慨が語られました。
ベンジャミン・ムートン氏(歴史的記念物名誉総監察官、歴史的記念物主任建築家)による基調講演2「ノートルダム大聖堂:新たなオーセンティシティに向けて」では、ノートルダム大聖堂で行われてきた修復(restoration)の歴史を中心に報告されました。まずフランスにおいて「モニュメント」という考え方がいつ誕生し、それらがどのように保存されてきたのかという視点から、フランス革命からベニス憲章、奈良文書にいたるまでの「モニュメント」理解の変遷が紹介されるとともに、フランスを中心に今日の欧州における遺産保存の理論的な条件が整理されました。次に、ルネサンスやロマン主義の建築観が主流を占めた19世紀以前の社会の中でノートルダム大聖堂が中世ゴシック建築の傑作という「モニュメント」として発見、評価されてきた歴史を背景に、19世紀にヴィオレ・ル・デュクらによって、中世ゴシック建築にみられる合理的精神を意識し、その材料や構法の保存を図りつつ当時最新の建築技術を取り入れた修復が実施されるにいたったことが説明されました。続いて、今回の火災による大聖堂の被害状況とともに、石材や木材の選定や加工の方法、ヴォールトや小屋組の再建、尖塔の復旧といった修復の各プロセスが豊富な現場写真を用いて紹介され、科学的な調査や歴史的な証拠に依拠することを前提としたベニス憲章に基づいて修復(restoration)が行われたことが強調されました。最後に、今回の修復工事における大聖堂のオーセンティシティを奈良文書との関連から改めてみた時、歴史上の様々な出来事が刻み込まれた建築物という物質的側面だけでなく、フランスのみならず世界の「モニュメント」として、様々な人々の思いに支えられた「生きている遺産」としての側面が意識されるようになったことが、大きな認識の変化として示されました。
田原幸夫氏(建築家、京都工芸繊維大学客員教授)による講演1「東京駅丸の内駅舎 保存・復原プロジェクト」では、ベニス憲章やドレスデン宣言に示された建築遺産保存の理念にひきつけながら、自身が主任建築家を務めた重要文化財東京駅丸の内駅舎の保存復原設計の考え方や同工事での取り組みについて報告されました。まず東京という大都市における丸の内地区と東京駅の歴史や位置付けが背景として紹介されたのち、今回の保存復原プロジェクトにおいては重要文化財としての遺産価値の保存と駅舎としての建築性能の確保の両立が大前提とされ、両者の適切かつ正当なバランスを確保することが最大の課題であったことが説明されました。その中では、遺産価値の保存については復原が目指す建築当初の大正期の姿のみならず戦後に存続してきた復興駅舎の姿にも十分配慮し、推測を排して科学的な調査に基づく復原を徹底したこと、また、新旧のバランスにおいてはその調和を図りつつ区別ができるように工夫したことなど、ベニス憲章の精神が強く意識されたことが説明されました。最後に、開業110年を迎える東京駅が最先端の現役施設として使い続けられている意義とともに、ドレスデン宣言で謳われた戦争で破壊された「モニュメント」の復原にもふれて、都市の建築遺産を「リビングヘリテージ」として受け継いでいこうとする意識や努力の重要性が述べられました。
呂舟氏(清華大学教授)による講演2「文化遺産の保護とオーセンティシティ:大上清宮を例に」では、1930年に焼失した道教の本山である大上清宮の再建プロジェクトを取り上げ、中国における文化遺産の「オーセンティシティ」の捉え方とその保護の現場での実践について報告されました。はじめに大上清宮の歴史や宗教施設としての位置づけが、美しい自然景観が拡がる立地とともに紹介され、材料、形状、技術、方法などあらゆる面から厳正な復元を目指した再建プロジェクトの概要が説明されました。再建プロジェクトの一環として行われた発掘調査では、宋、元、明、清の各時代にわたって積層した遺構が確認され、各時代の建築的な様相を知る手がかりが得られたことや、調査成果に基づく復元設計の中で行われた、遺跡の保存と宗教的な機能を両立するための工夫や展示上の仕掛けなどが豊富な写真とともに紹介されました。最後に、文化遺産保護の実践では、歴史的・文化的価値を遺産の価値として理解するだけでは足らず、現代的な要請とあわせて遺産の「オーセンティシティ」を判断することが必要であるとの考えが述べられました。
ディスカッションでは、稲葉信子氏(筑波大学名誉教授、放送大学客員教授)をモデレーターに迎え、3名の登壇者のほか、ゲストコメンテーターにジョージ・アブング氏(ケニヤ国立博物館名誉館長)と長岡正哲氏(ユネスコナイロビ支部文化局東アフリカ地域文化アドバイザー)の2名を加えて、奈良文書を契機として拡大あるいは拡散してきた文化遺産の「オーセンティシティ」という概念が、日本、フランス、中国、アフリカの文化遺産保護の現場で、いかに理解され、適用されてきたかについて議論が交わされました。「オーセンティシティ」とは文化遺産の価値の総体をみるものではなく、修復や改修などに伴って生じる個々の事象に際して、その考え方や手法の正当性を評価する指標となるものであるとする点で認識の一致がみられた一方、コメンテーターからは「世界遺産条約履行のための作業指針」に「オーセンティシティ」がきわめて限定的なかたちで明記されていることが、特に西洋由来の法体系をもつ旧植民地諸国にとって伝統的・土着的な文化遺産を世界遺産登録する上での障壁になっている、との問題提起がなされました。
最後に、岡田保良(文化遺産国際協力コンソーシアム副会長、日本イコモス国内委員会会長)の閉会挨拶では、奈良文書30周年ならびにベニス憲章60周年の節目にあたり、日本国内のみならず世界中で文化遺産の「オーセンティシティ」概念をめぐる議論が画期を迎えていることが述べられ、全てのプログラムを終了しました。
本シンポジウムは、会場に足をお運びくださった方々に加え、広く国内外からオンライン配信でもご視聴いただき、文化遺産学・建築学分野を中心に180名のご参加をいただきました。開催にあたりご協力いただいた関係各位ならびに参加者の皆様に対し、主催者より重ねて御礼申し上げます。
※本シンポジウムの内容については後日、報告書を公開予定です。また、当日の様子を収録した動画も、コンソーシアムYouTubeチャンネルにて公開予定です。是非チャンネル登録をお願いします。