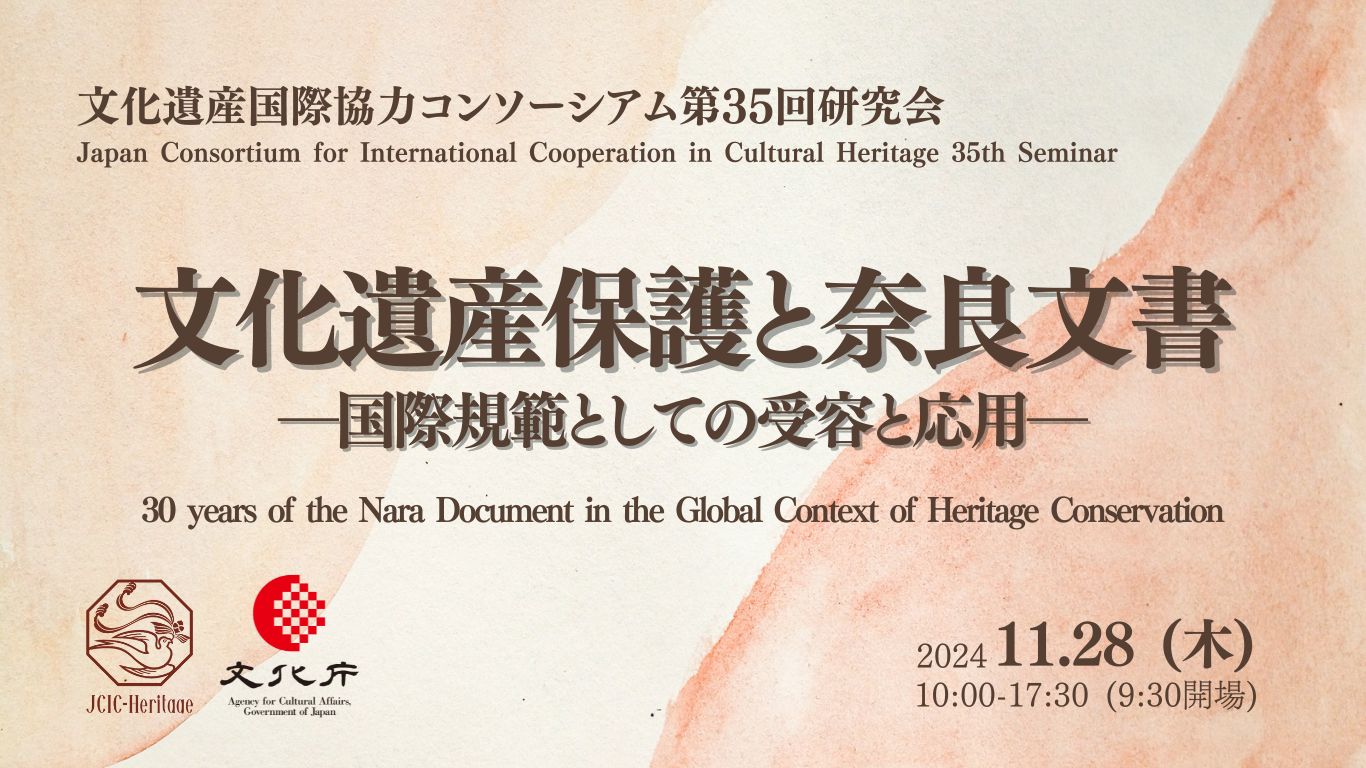文化遺産国際協力コンソーシアムでは、文化庁の共催、日本イコモス国内委員会の後援のもと、2024(令和6)年11月28日(木)に第35回研究会「文化遺産保護と奈良文書-国際規範としての受容と応用-」を、東京文化財研究所会議室にて開催しました。
※研究会の開催概要・プログラムについては、こちらをご覧ください。
「オーセンティシティに関する奈良ドキュメント」(奈良文書)の採択から30年の節目となる機会を捉えた本研究会は、世界の諸地域におけるオーセンティシティの概念の理解と実践をテーマに、海外招へいの専門家として、フランス歴史的記念物名誉総監察官・歴史的記念物主任建築家のベンジャミン・ムートン氏、中国・清華大学国家遺産センター長・教授の呂舟氏、ケニア国立博物館名誉館長のジョージ・アブング氏の3名を迎えて開催しました。
岡田保良副会長による開会挨拶と趣旨説明に続いて、ラウンドテーブル形式による3つのセッションを行いました。セッション1の「ヨーロッパ」では3名の専門家に報告いただきました。はじめに、ベンジャミン・ムートン氏から「ヨーロッパにおける遺産保護のオーセンティシティ」と題して、ヨーロッパにおける文化遺産の概念の歴史的広がりや遺産の価値、予備調査から始まる文化遺産の保存修復、そしてその後の活用に至るまでの大きな流れが報告されました。ヨーロッパの保存修復事業においては、現在でもベニス憲章が積極的に参照される一方で、木部の復旧を主体とした今回のノートルダム大聖堂の修復事業においてはベニス憲章だけでなく、奈良文書も保存修復の方針を補強する役割を果たしたと説明されました。
次に、坂野正則氏 (上智大学文学部教授)から「宗教的・感情的遺産と〈オーセンティシティ〉の関係性―パリ・ノートル=ダム大聖堂修復からの検討」と題して、信仰や感情といった無形的な要素がノートルダム大聖堂の修復事業に与えた影響や、宗教的遺産という性質上、宗教的儀礼の実施やキリスト教における聖遺物といった建築物以外の要素も同大聖堂のオーセンティシティを考えるうえで重要であることが説明されました。
最後に、アレハンドロ・マルティネス氏(京都工芸繊維大学デザイン・建築学系准教授)から「ヨーロッパにおけるオーセンティシティの概念の理解の多様性」と題して、木造建築であるノルウェーのウルネス教会とスペインのアニャーナ塩田の木造構造物を事例に、保存修復事業で考慮されたオーセンティシティが遺産毎に異なることが紹介されました。その中で、同じヨーロッパ内でもオーセンティシティの概念の理解は多様であり、文化遺産個々の価値に応じたオーセンティシティを検討する重要性が強調されました。
セッション1の発表を受けて行われたディスカッション1では、西和彦氏(文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室世界文化遺産部門主任文化財調査官)のモデレートのもと、各発表で取り上げられた事例を振り返り、ヨーロッパにおける文化遺産の保存修復の文脈での奈良文書やベニス憲章の位置づけについての論点が整理されました。奈良文書が明示的に語られることは少ないものの、オーセンティシティを考えるうえで、地域性を重視するという精神が確かな影響を及ぼしていることが確認された一方、多様化が進む建築遺産の保存における今後のオーセンティシティのあり方についても様々な意見が交わされました。
セッション2の「アジア」でも、3名の専門家に報告いただきました。はじめに、呂舟氏から「中国の文化遺産保護におけるオーセンティシティ」と題して、中国におけるオーセンティシティの捉え方の歴史的変遷が報告されました。2015年に改訂された中国文物古跡保護準則で明示された通り、従来から評価の対象であった歴史的、芸術的、科学的価値といった有形物に偏った遺産の見方から、文化的、社会的価値も考慮した、より包括的な遺産の価値評価に視野が広がり、文化的伝統の継承の実現をも目指す文化遺産の保存修復が実施されるようになってきていると説明されました。
次に、ウーゴ・ミズコ氏(学習院女子大学国際文化交流学部教授)から「古材の有形的な価値―日本の歴史的建造物の保存修理を例に―」と題して、「世界遺産条約履⾏のための作業指針』におけるオーセンティシティの定義を振り返るとともに、重要文化財に指定されている日本の建築遺産の保存修復事例について、部材の取り扱いと伝統技術に関わる伝承のあり方に着目し、保存修復の新技術の導入と伝統技術との両立に対する問題提起がされました。
最後に、下間久美子氏(國學院大學観光まちづくり学部教授、日本イコモス国内委員会副委員長)から「日本の文化財保護と世界遺産の仕組みの比較によるオーセンティシティの考察」と題して、日本の文化財保護の体系に内在する建造物および伝統的建造物群のオーセンティシティの捉え方について、世界遺産との比較をもとに報告されました。その中で、文化財保護実務における住民主体のアプローチや「文化的な質」を次世代に伝えていくことの重要性が強調されました。
セッション2の発表を受けて行われたディスカッション2では、友田正彦氏(文化遺産国際協力コンソーシアム事務局長、東京文化財研究所副所長)のモデレートのもと、日本や中国、その他のアジア諸国における建築遺産のオーセンティシティに対する理解やその保存修復、復元の方法論に横たわる差異があらためて認識されました。奈良文書が提起したように、文化遺産毎の価値評価に基づいたオーセンティシティや遺産保護の適切な方法を考えていくことが重要であることが確認されました。
セッション3の「アフリカ」でも3名の専門家に報告いただきました。はじめに、ジョージ・アブング氏から「アフリカにおける遺産のオーセンティシティ」と題して、自然やコミュニティと密接な関係の中に存在するアフリカの遺産のあり方について報告されました。継続性を持ちながらもその時代に応じて変化を続けるアフリカの遺産は、有形物というよりも、コミュニティの伝統的な知識や慣習等の無形的な要素を主体として保護、継承されてきたものであり、このような変化や継続性を世界遺産の文脈に位置付けるうえで奈良文書は重要な役割を果たしているものの、アフリカの遺産のあり方に適応したオーセンティシティの捉え方を確実なものにしていくには、さらなる議論と実践を重ねていく必要があることが強調されました。
次に、岡崎瑠美氏(芝浦工業大学建築学部准教授)から「アフリカにおけるコミュニティ包括型建築遺産」と題して、エチオピアの世界遺産の事例を通じて、いかにコミュニティが遺産の保護と継承に密接に結びついているかが報告されました。アフリカ諸国における劇的な人口増加や経済発展に伴う都市開発の影響で、消滅の危機に直面しているコミュニティの問題や、それに伴う建築遺産の危機についても触れられ、コミュニティが現在おかれている状況の把握や、それに付随する遺産の存在を記録していくことが急務と指摘されました。
最後に、長岡正哲氏(ユネスコナイロビ支部文化局東アフリカ地域文化アドバイザー)から「現代の遺産論における課題―理論と実践におけるアフリカの遺産の真正性に関する事例研究―」と題して、ユネスコのグローバルストラテジーの採択から30年を経たいまも、世界遺産リストに占めるアフリカの遺産の数が少なく、地理的な不均衡が厳然と存在することが指摘されました。一方で奈良文書の採択後、アジア地域の世界遺産の数が劇的に増加したことを引き合いに、今後、アフリカの遺産に適応したオーセンティシティを確立していく重要性と、そうした考え方を反映した「世界遺産条約履⾏のための作業指針」の改訂の必要性を訴えられ、現在、そのための具体的な準備を進めていることが報告されました。
セッション3の発表を受けたディスカッション3では、長岡正哲氏のモデレートのもと、法制度の脱植民地化やアフリカ独自の遺産の定義の必要性、開発に伴い破壊の危機にある遺産の記録、伝統的な知識を保有するコミュニティのエンパワーメント等のアフリカの遺産が直面している課題が共有されました。真の意味で人類共通の遺産を実現するためにも、ベニス憲章や奈良文書に続く、アフリカの遺産の性格やオーセンティシティのあり方を包含した考え方を確立していく必要性が提起され、ユネスコナイロビ支局が主体となって2025年5月に開催を計画しているナイロビでの国際会議がその足掛かりとなることを目指していることが確認されました。
これら3セッションの終了後、河野俊行氏(九州大学名誉教授、イコモス名誉会長)のモデレートのもと、コメンテーターに西村幸夫氏(國學院大學観光まちづくり学部長)を迎え、全ての登壇者が参加するパネルディスカッションを行いました。はじめに、西村氏から、自身も参加した1994年の奈良会議と10周年と20周年に行われた会議の議論を振り返り、本研究会での議論が奈良会議以降積み重ねてきた世界遺産のオーセンティシティに関する議論を継続し、深化を図っていくものになるという期待が示されました。その後の登壇者全員での議論では、遺産の多様化に応じて、ますます複雑になる有形遺産と無形遺産、文化遺産と自然遺産、そして遺産に関わる様々な利害関係者との関係の中で、遺産のオーセンティシティはインテグリティと比較して、議論の余地が多方向に広がっていっていること、また、そうした議論の中には、開発や紛争といった社会問題との関係も切り離せないことなど、登壇者の多彩な活動を反映した多角的な視点からの幅広い意見が交わされました。
パネルディスカッションでの議論は伯仲し、まだまだ続く様相でしたが、あえなく時間切れとなり、青木繁夫副会長による閉会挨拶をもって、研究会は終了しました。
本研究会は、会場に足をお運びくださった方々、国内外から広くオンライン配信で視聴くださった方々をあわせると、100名を超える方々にご参加をいただいたイベントとなりました。
また、本研究会の「セッション1:ヨーロッパ」にいて、機材トラブルによりオンライン配信が正常に行われず、皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、この場をかりて、あらためて心よりお詫び申し上げます。今後は同様のトラブルが生じないよう再発防止に努めて参ります。
本研究会の開催にあたり、ご協力いただいた関係各位、ならびに参加者の皆様に対し、主催者より重ねて御礼申し上げます。
※後日、本研究会の報告書を公開予定です。また、研究会を収録した動画も、コンソーシアムYouTubeチャンネルにて公開予定です。チャンネル登録もぜひお願いします。